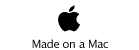英語茶房の つれづれ談話 Random Essay
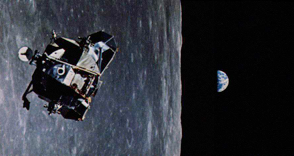
小説などを翻訳する人は「翻訳家」と呼ばれることもあるようです。翻訳家となるとそれはそれは英語(その他外国語)を的確に理解し、すぐれた日本語にすることができるのでしょう。
でもたまにがっかりします、英語を正確に発音できないということに。
annihilate を「アニヒレート」とルビを振る。annihilator という恐ろしい武器がSFにはよく出てきます。この間亡くなったハードSF作家、ジェイムズ・P・ホーガンの名著「星を継ぐもの」(原題 Inherit the Stars) でも登場する武器ですが、そのルビが「アニヒレーター」になっています。そして、スケールの大きなSF・ファンタジー作品を得意とする漫画家、星野之宣によるマンガ版「星を継ぐもの」でも、そのまま「殲滅兵器 アニヒレーター」が使われています。
「翻訳家」と呼ばれるからには、すばらしい翻訳文を書かれるのでしょう。だったら、発音くらいは正しく知っておいていただきたいものです。annihilate は「アナイアレイト」ですから、annihilator は「アナイアレイタ」。h は無音です。
そんな例は映画の題名にも現れます。
チョウ・ユンファのアメリカ製冒険活劇映画「Bulletproof Monk」は「バレットモンク」という和名になっています。いつから bullet (弾丸)が「バレット」になったのでしょうか。おそらくこれ以降だと思いますが「バレット」のオンパレード。Google してみると、「バレットストーム」(ビデオゲーム)、「バレットタイム」(撮影技術)、「バレット・ブレイク」(映画の邦名)などなど。さらに塚本晋也監督によるマニア的人気を誇る全編セリフが英語の作品「鉄男 The Bullet Man」。同作は日本語では「バレットマン」と発音されています。
誰かが、おそらく字幕翻訳者が最初に bullet を「バレット」と読んだのでしょう。素人じゃないです。bullet の bu を「バ」と読むと言うことは、例えば but などからの知識にもとづくものです。ローマ字読みだったら「ブ」になりますから。ただこの場合には「ブ」で正解でしたが。
映画関係者はまったく疑問に思わなかったのでしょうか。「バレットモンク」でも英語のセリフを聞いていれば何度も「ブリット」と発音しているはず。「鉄男」でも、アメリカ人俳優を使っているわけで、そこでもきっと「ブリット」という発音は出ているはずです。なのにどうして「バレット」になるのか。
他にも acoustic が「アコースティック」(本来は「アクースティック」)というのがあります。これは音楽関係者が広めた発音だと推測されます。acou を「アクー」と言えなかったのでしょうか。
ubiquitous を「ユビキタス」と発音したのは、学者の方でしょう。きちんと英語を発音すれば「ユビクイタス」になりますが、どうしてか「qui」を「キ」と発音したのです。フランス語では qui を「キ」と発音するので、フランス語読みか、と思いましたが、それはないでしょうね。コンピュータ技術はアメリカが最先端ですから、その学者先生も英語の発音を最初に聞いたはずです。「クイ」では「指杭」になってみっともない、と思ったのでしょうか。
これらの例は、日本人が(日本人だけかどうかわかりませんが)いかに「英語の音に無関心か」を表していると思います。
母国語が似た文法形態を持つ韓国は、といえば、彼らはもっと原音に忠実です。ハングルはより細かい音を表すことができる文字ですから、例えば「マッカーサー」は「맥아더(メカサ)」のように書かれる。英語の「machine」を日系人が「ミシン」(実際は sewing machine の「ソウイング」が省略された)と聞こえたまま発音したのと似ています。
「英語の発音にこんな無頓着な日本人は、だから英語が下手なんだ」をあながち否定できませんが、英語を専門とする翻訳者だったら英語の発音に敏感であることが常識であってほしいです。
もっとも「英和翻訳をする人は英語があまりしゃべれない」とは昔から聞いていました。実際そうなのかどうかは確認していませんが。特に文芸翻訳者(家)は、「英語から日本語に翻訳する」ことがほとんどで「日本語に翻訳することが好き(得意)」なのであって、必ずしも「英語をしゃべることが好き」なわけではないようです。確かにいくら英語の発音をよく知っていて完璧に発音できても、翻訳した和文が下手なら翻訳者としては何の意味もないですけれど。
「音に敏感であれ」はやはり「話す英語」の上達には不可欠だと思います。
翻訳者(家)の哲学
2011年5月31日火曜日